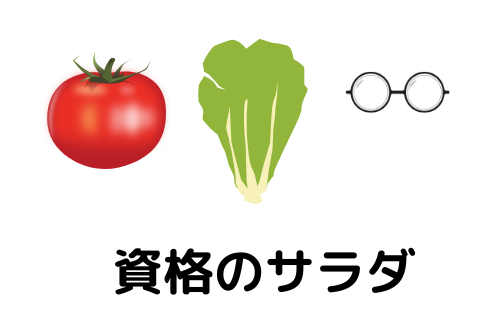英語チームの刺激に背中を押されて
今週、職場の英語支援チームの総会に参加しました。
業務の合間のボランティア的な活動とはいえ、集まったメンバーの志の高さに驚かされました。
英語で発表をこなす人、翻訳を学び続ける人、TOEIC900点を目指す人。
それぞれが「自分なりの英語」を追いかけている姿に、静かな刺激を受けました。
会合を終えたあと、胸の奥に小さな火がともりました。
──「自分も、もう一度やってみようかな」と。
帰宅後、過去10年間のTOEICスコア表を眺めてみると、去年は無対策で640点、一昨年は745点。
点数の上下はあっても、毎年受け続けている自分が少し誇らしく感じました。
そして気づけば、TOEIC公式サイトの申込ページを開いていました。
申込ボタンをクリックした瞬間、「ああ、今年もこの季節が来たな」と、妙な充実感がこみ上げてきました。
これで11年連続のTOEIC受験。
年甲斐もなく英語に火がついた夜でした。
続けてきた理由と、触発の力
TOEICを受け続ける理由を、あらためて言葉にするのは難しい。
800点を取りたいからでも、転職のためでもありません。
もはや「英語力を測る試験」というより、「学びのリズムを確認する儀式」になっています。
12月上旬、恒例の人間ドックの翌週にTOEIC。
体の健康診断のあとに、言葉の健康診断を受けるような感覚です。
点数よりも、「自分はまだ英語に関心を持っている」──その事実がうれしいのです。
今回の申込は、まさに英語チームの仲間たちのおかげ。
彼らの熱意に刺激され、一晩経ってもその余韻が消えませんでした。
触発→行動→継続。
このリズムこそ、学びを支える黄金パターン。
年齢や役職を問わず、人からもらう火花が自分を動かす瞬間ってありますよね。
年甲斐もなく動けるうちは、まだ若い
英語チームの仲間に刺激され、TOEIC11年連続チャレンジを決めた。
こうしてまた、机の上に公式問題集を広げる週末を迎えられる。
それだけで、心が少し軽くなります。
「年甲斐もなく動けるうちは、まだ若い。」
資格ブロガーとして、そしてひとりの学び人として。
12月7日(土)、11年目のTOEICが待っています。
🪶 試験の翌日はジョン・レノンの命日。
“Imagine”を聴きながら、今年も静かに“英語の旅”を締めくくる予定です。