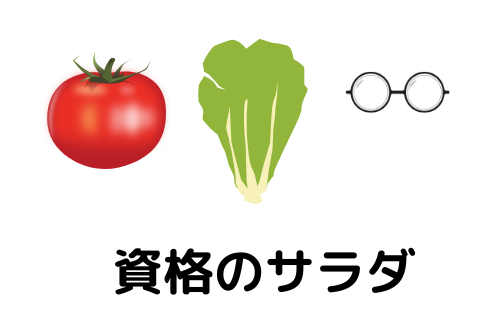― 渡英シスから東京ドームへ
はじめに:ロックと英語のあいだで
英語を学び始めたきっかけは、テストや資格のためだった。
けれども、いつの間にか「言葉そのもの」に惹かれるようになっていた。
そして、その感覚を決定づけたのが、イギリスのロックバンド「オアシス」だった。
2025年7月。私はロンドン・ウェンブリーで、再結成したオアシスのライブを体験した。
その瞬間、教科書の中の英語が、現実の息づかいを持ちはじめた。
観客が大合唱した “Don’t Look Back in Anger” の一節。
「怒りにとらわれるな」――まさに、英語が心を揺さぶる瞬間だった。
資格のために覚えたフレーズではない。
それでも、意味がすっと胸に落ちた。
その体験こそ、私にとっての“渡英シス”=英語の再出発だった。
ロンドンで見つけた「生きた英語」
現地では、日常の会話や街の看板に触れるたび、
“英語が文化とともにある”という実感を得た。
例えば、地下鉄の案内「Mind the gap(足元に注意)」――
単なる注意書きのようでいて、
「間(ま)を意識せよ」という、イギリス的な感性を感じた。
ホテルの受付で交わす “Cheers!” は、「ありがとう」でもあり「ごきげんよう」でもある。
この一言に、イギリス人の距離感の取り方が詰まっているように思えた。
オアシスの歌詞もまた、こうした文化の中から生まれた。
たとえば “Wonderwall” は、「心の支え」という意味で使われる。
単なる恋の歌ではなく、誰かを信じる力のメタファーだ。
辞書だけではたどり着けない、生きた英語表現がそこにある。
東京ドームで、英語が“響く”瞬間
そして2025年10月。
同じオアシスが、今度は東京ドームにやってきた。
ロンドンと同じ曲、同じ兄弟、同じ大合唱。
けれども、聞こえ方はまるで違っていた。
“Don’t Look Back in Anger” のサビを歌うとき、
あのウェンブリーの空気がよみがえった。
英語の一語一語が、もはや「学ぶ対象」ではなく、
心の奥に染み込む“記憶のスイッチ”になっていた。
その瞬間、思った。
英語は勉強するものではなく、
「経験するもの」なんだ、と。
英語の資格と、心の英語
もちろん、英検やTOEICといった資格の勉強も大切だ。
私も毎年、TOEICを「英語の健康診断」として受けている。
語彙力や文法力を磨くことは、英語を“使う土台”になる。
だが、資格だけでは見えてこない世界がある。
ロックの歌詞や海外の旅を通して、
「言葉が人をつなぐ瞬間」に触れると、
資格勉強のモチベーションが変わる。
“点数のための英語”から、“人生を豊かにする英語”へ。
オアシスの音楽は、私にその切り替えを教えてくれた。
英語を通して世界とつながること。
それこそが、資格を超えた「学びのゴール」なのだと思う。
まとめ:英語を“体験”しよう
「資格のサラダ」は、英語・貿易・不動産など、
さまざまな学びを“生活に取り入れる”ことをテーマにしてきた。
今回の「オアシスで学ぶ英語」も、まさにその延長線上にある。
英語を学ぶ動機は、人それぞれ。
けれども、心を動かされた瞬間こそが、最大のモチベーションだ。
ロンドンで見た景色、東京での大合唱――
そのすべてが、英語という言葉をもう一度信じさせてくれた。
これからも私は、
ロックを聴き、旅をしながら、英語を学び続けるだろう。
「資格の英語」も「心の英語」も、どちらも自分の一部として。
Don’t look back in anger.
怒りではなく、希望を胸に。
それが、私の英語との向き合い方である。