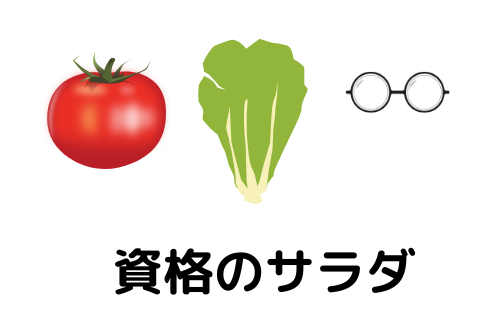悔しさこそ合格のバネ(ギャフンと言わせよう)
私が宅建士に合格できたのは、学生時代のJ先輩のおかげである。
別にJ先輩に指導をされたわけではない。
むしろ反骨精神とか半面教師で、宅建士にチャレンジして不合格になったJ先輩にギャフンと言わせたくて、宅建士の勉強に勤しみ、身を結んだ。
資格試験に勝利するには、そういう腹黒いモチベーションやしたたかさは、アリではないかと思う。
1.宅建不合格先輩の言い訳
学生時代、サークル活動の一環で、(部室を借用している手前)街頭募金活動への参加というのがあった。しかし、J先輩の野郎は、宅建の試験が近いとかなんとかぬかして、この募金活動を拒み続けた。結果、宅建では、J先輩は宅建不合格。募金をやりたくないから、その言い訳に宅建受験をダシにしたウワサがある。
同じサークルでは、宅建受験を目指したものの(ちょっとした宅建ブームだった)挫折した者が後を絶たなかった。
私は、J先輩とは学年は違うけれども、同じ主任矜持の民法(物権法)ゼミを専攻した。(ちなみに、卒業論文は、区分所有権法(マンション法))ゼミのT教授は、ことあるごとに「ウチのゼミ生ならば、宅建をチャレンジしなさない。持っていて損はないから…」と何度も言っていた。
J先輩もT教授の宅建のススメに感化されたと思う。
民法ゼミ専攻、卒論はマンション法、こういう経歴では、さぞ不動産業界に関心があるのかと思われるかもしれない。けれども全く興味がなかった。
ただ、海が見える職場で働きたい(もちろんそれだけの理由ではないけれども)、貿易業界に就職した。
貿易業界では、宅建士よりも通関士の方が重宝されるので、まずは、通関士にチャレンジ。座学と実務経験で、難なくクリア。その勢い余って、ずっと心残りだった宅建士にチャレンジがはじまった。
2.宅建スクールの受講
独学では合格は難しいと判断した私は、毎週土曜日に開講していた、TAC専門スクールに通い、そこに勉強の主軸とした。
大教室で行われる宅建講座、なるべく前の方に座るようにした。また、講師が呼びかけた「懇親会」にも参加。宅建講師や受験生仲間とリアルな交流を深めた。
(こういう人間関係は、孤立になりやすい資格試験対策では重要です)
宅建の勉強を始めて驚いたのは、通関士試験の経験が役立ったことである。
具体的には、宅建士で出題される「宅建業法」が、通関士の出題科目の「通関業法」と、ほとんど構造が似ているということであった。宅建業者と宅建士(宅建取引主任)の関係は、通関業者と通関士の関係のそれと酷似している。
こういうのは、貿易業界に身を置く者として、経験が生きることになる。
(J先輩を持ち出すわけでもなく、このあたりのイメージは学生さんは不利かな?)
そして宅建士の試験当日、満を持して試験会場のある県庁所在地まで出向く。
合格発表の日、当時は、名前が県民紙に掲載されていたので、祈るような気持ちで、名簿を見た。自分の名前が載っていたことを、偉く喜んだ記憶がある。
(そういえば、通関士試験も、当時「貿易実務ダイジェスト」という雑誌に合格者の名前が掲載されていた)
宅建に関しては、初チャレンジで一発合格。
民法ゼミで培った民法知識、通関士試験対策で思わぬ成果を上げた宅建業法、さらには、宅建スクールに通って、身銭を切ったことが、宅建勝利への秘訣であった。
3.宅建合格のメリット
では、せっかく宅建士に合格しても、宅建・不動産業界に進まなかった私として、そのメリットはあったのだろうか。
答えは「イエス」である。
まず、自分自身の賃貸アパートを借りるとき、海千山千の不動産屋さんと互角に渡り合えることができる。宅建有資格者ということで(ことさらひけさらすことはないけれども)、物件案内や重要説明など、不動産取引をめぐるプロセスに明るいので、不動産選びに失敗することはない。(過信は禁物です)
所帯を持ち、マンションを購入することになっても、同様、不動産屋さんや銀行さんとのお付き合いになるので、こちらも、高額商品ゆえ失敗は許されない。
宅建を持っていることで、ある程度の不動産の知識は身に付いているので、自分の決断の揺るぎなさの一介になる。
さらにある程度、年齢を重ねると、肉親や親戚がお亡くなりになる、ということがある。人が無くなると「不動産が動く」ことになる。
さすがに相続をめぐる争いはないが、不動産を継承するにせよ、処分(売却)するにせよ、宅建士としての知識があれば、不動産取引のルールがなんとなくわかる。
親戚筋からも一目置かれる存在になり、納得のいく相続へ宅建の知識が寄与する。
仕事に役立つべき宅建だが、実は、貿易業界でも役立った。
あらゆる売買契約は、民法が基礎となるし、貿易では物流会社とのお付き合いが欠かせないが、物流倉庫の賃貸借契約書や登記書類を、宅建資格者ならば、「書面が読める」社内でも重要なキーパーソンになれる。
要するに、不動産に明るい人が少ない貿易業界で「宅建士」という経歴は、自分の個性をいかんなく発揮できる「強み」である。
不動産業界ではなく、あえて貿易業界に身を置く人間として「宅建士」の取得はひとつの選択であり、個性でもある。
4.まとめ(資格に損なし)
そして最後に、宅建士合格で最大のメリットを紹介しておく。
それは、宅建士に合格したという「自信」である。
だから貿易業界に努める私が、仕事がイヤになったとき、「自分は宅建士を持っている。だからこんな会社、いつでも辞めてやる」という腹をくくれる覚悟が持てることが最大のメリットである。
こうした覚悟が、何度も危機的状況をやり過ごしてきた。
同じ会社を20年、30年勤めれば、嫌なこともいくつか直面するだろう。
結局、私は、貿易業界にずっと身を置いているが、宅建合格(合格の価値は一生続く)という誇りがあるからこそ、仕事がイヤになっても気持ちが切り替えられる。
貿易業界の人間として、英語や通関士の資格はもちろんだけれど、あえて宅建士という「ずらし」を行うことで、かえって心理的負担に余裕ができる。
もしも、宅建士に興味があり、異業種なので勉強に躊躇している人がいれば、心配は無用である。努力は決してムダではないし、資格は、人生そのものを豊かにする。
だから迷ったら、宅建士の勉強をはじめましょう。