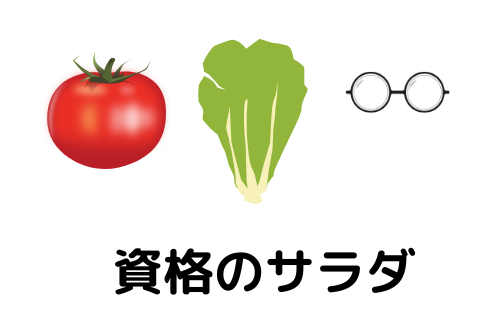(はじめに)通関士試験の合否のカギを握るのは「計算問題」
通関士試験では、計算問題がキモとなる。
実際、学習を挫折していまう人は、輸入申告特有の「関税・消費税の計算」で頓挫していく人が多い。計算問題に関しては、理屈や知識ではない。実際の計算をこなして、カタを覚えるしか対策がない。
日本関税協会が出版している「計算問題ドリル」を利用するのがおススメである。
これから通関士を目指す人には、全般的に勉強するよりも、難敵の「計算問題」に特化した同書によるトレーニングを積んた方がいい。
1.通関士の計算問題とは?
そもそも輸入申告には、関税、消費税、地方消費税、(酒税、石油石炭税などの)内国消費税がかかり、これを収めなければ、輸入許可ができない。
関税には、従価税率と従量税率(さらにはこのふたつを併せ持つ従価重量税とがある)がある。
従価税とは、取引価格が課税標準となり、これに税率をかけて算出することである。
平たくいえば、貿易取引額に応じた税率が適用される。
一方、従量税とは、輸入しようとする物品の数量を課税標準としている点に違いがある。取引価格に関係なく、たとえば酒税であれば、リットルあたりの税額、タバコ税ならば、タバコの本数あたりの税額が、算出されることになる。
(実務上は、従価税の利用が圧倒的に多い)
これを聴いただけでも、逃げだしたくなる人が多いことでしょう。
さらには通関士試験では、関税・消費税等の不足額を積み増す「修正申告」や、納め過ぎた関税・消費税等を還付や充当してもらう「更生の請求」というものがあり、これも計算問題として出題される。
さらに本来、支払われるべき税額を納付していない場合に(関税とは別に)支払われる「延滞税」、申告が適正に行われていない場合にペナルティ的側面として支払われる「加算税」なども出題されます。
実際、税額の出し方は、法律(関税法、国税通則法)に細かく規定してありますが、これを読んでも到底、一般人には理解できません。
そこで、計算問題の数をこなして、苦手意識をなくすことが、通関士合格のために、最初に取り組むべきことです。
2.通関士の計算問題は実務経験者でも難しい
こうした計算問題は、プロの通関士や監督官庁の税関職員ですら、迷うこともしばしばで、難しくて頭の痛いところです。
実務的には、電子輸入申告(NACCS)が導入されて、課税価格と税番(タリフによって細かく決められた品目分類の番号)を入力することによって、自動計算で出てくるので、電卓を叩いて、税額を出すことはしていません。
(だから、実務の先輩も「計算問題」に関しては、きちんと教えてくれる人が少ないのです)
ただし、自動計算される税額も、そもそもどういう計算(端数処理を含めて)で成り立っているのか、通関士になろうとする人は最低限、知ることが必要です。
実務においても、NACCSによらないマニュアル申告や、手計算による「検算」なども必要でしょう。
一方、実務のベテランや先輩は、税額の出し方を身に染みて知っている一方、それを言語化して、ビギナーに教えることが難しいのです。
私も、通関士試験を合格し、貿易実務に長く携わっていいる人間ですが、数字にはめっぽう弱いです。では、どうしたら、税額の計算を身に付ければよいでしょうか。
これはもう、「計算問題ドリル」を入手して、コツコツと基礎から勉強するしかありません。
ドリルをこなすことで、わかりにくい関税の出し方が、わかりやすく身に付くことできます。
計算問題に特化した「計算問題ドリル」は、通関士試験を目指す人ばかりではなく、なんとなくうろ覚えで、職場の後輩やビギナーに教えることになる実務者も、必携の学習教材です。
私も、職場で、関税・消費税の出し方を後輩に聞かれて、答えに窮したことから、慌てて週末に「計算ドリル」を手に入れ、基礎から勉強し直しています。
3.まとめ(通関士試験の計算問題から始めよう)
通関士試験対策本は、やはり50年以上の実績のある「日本関税協会」が出版している書籍が良いでしょう。
値段は少々高めですが、実務に則していることから、実際、独学で通関士試験を目指す場合、「かゆいところに手が届く」作りになっています。
先に紹介した「計算問題ドリル」のほか、申告書作成問題対策に特化した「ゼロからの申告書」、課税価格を決定するためのルールを網羅した「関税評価ドリル」など、専門分野に特化した書籍が豊富です。
特に、計算問題は、理屈や知識では太刀打ちができません。
だから、通関士試験を目指す人は、他の分野に先行して「計算問題ドリル」だけは手に入れて、電卓片手に、厄介な計算問題を「頭の体操」と割り切って、苦手意識をなくすことが先決です。
分厚い総合参考書「通関士試験の指針」、や過去問題集の「問題・解説集」を揃えるのもいいですが、ボリュームの多さに圧倒されて、挫折を招いてしまっては、元も子もありません。
通関士は一年に1回の勝負。だからこそ、確実な戦略で1年スパンで学習を進めていきましょう。
挫折をしないコツは、わかりにくいことをわかりやすく、楽しく学ぶこと。
「計算問題ドリル」で、税額の出し方そのもののプロセスを愉しみましょう。