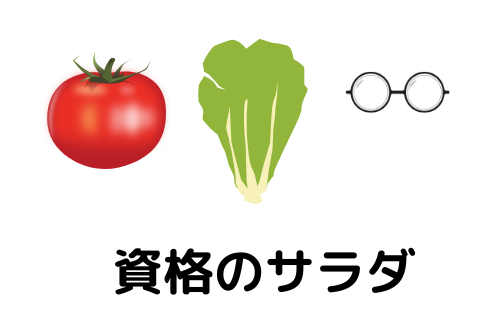勤めながら英語の勉強は大変である。
しかし、これからの時代、英語を避けては通れない。
まずは、英語資格のパスポートである「英検2級」を目指しましょう。
私は、学生時代は「英語」とは無縁の生活、いや、どちからかといえば、英語には一定の距離(苦手意識)置いていた。新入社員の頃も同じ。英語は気になるものの、社内の選考試験に落ちたことなどもあり、英語の出来る人は羨ましいと思いつつ、自分には関係のないことだと思っていた。
30代になって、一発奮起した。
英語能力のデフォルト(初期値)が「英検2級」だったこともあり、まずは独学で、英検2級のチャレンジがはじまった。
これから独学で英検2級に合格したい人のために、自分の経験を元に効率的な合格勉強法をアドバイスしていきたい。
1.単語力強化
とにかく、英検試験は「単語力」の勝負。
旺文社の「英検2級でる順パス単」を手に入れよう。
これはハンディサイスのため、片時も離さず、持ち歩き、スキマ時間があればパラパラと目を通すクセをつけよう。
私の場合、わからない単語は「書かないと覚えられない」性分である。
そんな人には、副教材の「パス単書き覚えノート」が重宝する。
「パス単」に連動して、実際に書くことで、単語力を増やすことができる。
単語は、書いて覚えるとともに、耳から覚えることも重要である。
そんな時は、パス単の「音声ダウンロード」を活用して、耳から単語力の増強を図っていこう。
英検試験は、まず前半に「語彙力」を試す問題が出てくる。
一定の単語力がないと太刀打ちできない。
忙しい社会人ならば、一定時間、勉強する習慣をつけよう。
そして、まずは、朝に「パス単」を使った、書き覚えをすることで、朝のボーッとした頭を退治し、「英語学習脳」「英検チャレンジモード」に切り替えよう。
2.勉強習慣化
英検にせよTOEICにせよ、目標を達成するには勉強の習慣化が必要。
さすがに「パス単」を眺めているだけではメリハリがつかない。
旺文社「英検2級集中ゼミ」という書籍を手に入れて、毎日の勉強の軸としよう。
英検2級に独学でチャレンジするならば、夜型から朝型に切り替えよう。
朝こそ勉強する人にとっては、未知のフロンティアである。
朝、1時間早起きして、机に向かおう。
私の場合、朝はまだ家族の者が寝ているので、リビングで、英語の勉強できる環境を確立した。テレビや動画視聴、ゲームなどで同居家族がうるさい夜に比べて、朝は静かなので、勉強に集中できる。
長距離通勤の場合、1時間ほど早めに出勤して、職場で始業時間まで勉強したこともあった。職場近くにカフェがあれば、そこを利用してもいい。
パス単の書き覚えノートで「目覚めた」あと、毎朝、30分、「集中ゼミ」にとりかかろう。
数ある対策本の中でも、「集中ゼミ」こそが、英検で出題される4技能のうち、とりあえず一次試験突破に特化しているので、学習の計画が立てやすい。
(スピーキング能力については、まずは、一時合格の段階では不要である)
朝が苦手な人は、ひとまずツイッターに「つぶやく」ことを勧めたい。
多くの朝勉の人とつながることで、ヤル気が出てくるはずである。
3.休日は過去問題
平日は、「パス単」て単語力、「集中ゼミ」で総合学習を積んだら、ぜひ休日は、化問題を使って「模擬試験」にチャレンジしてもらいたい。
旺文社の「英検2級過去6回全問題集」では、本番さながらのフォーマット、さらに、自動採点機能がついているので、自分の苦手科目を図式化して教えてくれるので、学習の計画とモチベーションアップにつながる。
ここでも「朝型学習」が効果的である。
休日も早起きして、朝の2時間、自分の勉強のために「予約」をしよう。
結局、過去問題にチャレンジしようと決意するものの、なかなかお休みの日は、習慣化が難しい。朝は勉強することと割り切ってしまえば、平日の1時間、休日の2時間を英検対策に充てることができる。
昼間であると、勉強を中断せざるを得ないことが発生しやすい。
朝であれば、誰にも邪魔をされることなく、本番さながらの「過去問題」をやり通すことができる。
過去問題は「繰り返しやる」ことが前提になるので、問題に直接、書き込みはしない方がいいい。予想選択肢に「しるし」をつけたりすると、二回目以降の試験では、それが気になる。TOEIC試験ではないので、本番は、線引きや「しるし付け」のやり放題の英検であるが、独学での学習では、繰り返してやることを前提に、問題への書き込みは控えよう。
4.まとめ(習慣化)
英検2級に独学で合格したい人には、
・毎日の単語力増強
・主軸教材で習慣化
・休日は過去問題
この三つのメソッドは不可欠である。
そして何より「毎日の学習の習慣化」を確立するために、ぜひ「朝勉」「朝活」をおススメしたい。
「朝を制する者は資格を制す」
挫折しそうになったら、朝の勉強成果をツイッターでつぶやいてみよう。
きっと、アナタのがんばりを「わかってくれる人」が現れるはずである。