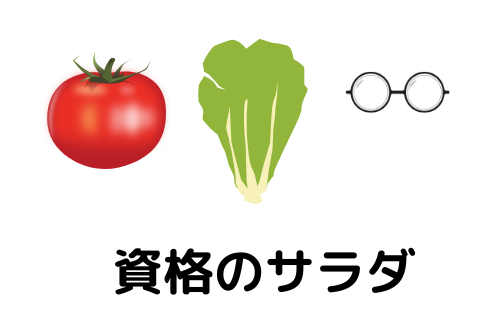「英語を勉強したいけれど、なかなか学習時間が取れなくて…」
こんな声をよく耳にする。
忙しい社会人なら、いかに効率的に英語学習時間を確保するか。
早起きして、朝の勉強、会社近くのカフェや始業時間前の職場で勉強。
さらには、昼休みや通勤時間…。
涙ぐましい努力で時間捻出に勤しむことになる。
けれども社会人にとって、いちばんマネジメントしたいのは、「会社にいる時間」である。そう、一日の大半を過ごす「会社で」英語を勉強できる機会ができてたら、素晴らしいことである。
「いやいや、別に英語なんてまったく業務と関係ないし…」
そんな反論が聞こえてきそうだが、果たしそうだろうか?
英語を使わない仕事であれば、無理矢理「英語化」してしまうのはどうだろうか?
私がおススメしたい会社で学ぶ英語ツールは「バイリンガル名刺」。
これさえ実践できれば、まったく英語が使わないと嘆く前に、英語を学ぶ環境が整えられる。
1.バイリンガル名刺の威力
会社人間にとって必須のツール、それは「名刺」である。
もしも英語学習に興味がある社会人で、自分の名刺が「日本語」しか書かれていないのならば、すぐに「日英併記」に切り替えよう。
「いやいや、英語の名刺なんて配る機会がないし…」
そんなことを言ってはダメ。何事も「カタチ」から入るのが上達のコツ。
ここで気を付けてもらいたいのが、英語版という「二枚目の名刺」を持つことではない。勘違いしてもらいたいくないのは、しょせん、日本の会社人間は、日本語を超えられないのである。
カタチから入るといっても、やれ英文ディベートだの英字新聞だのと「日本語から離れた」アイテムに凝って、結局、よくわからなくて、英語そのものを挫折してしまう人を何度も見てきた。(自分もそうだった…)
日本語でやる仕事を大切にしつつ、願わくば英語でやる仕事の機会を、無理のない範囲で関わってみたいな、というスタンスが大切である。
何事も無理は禁物である。
英語版オンリーの「2枚目の名刺」を作成したところで、配る機会がなく、自己嫌悪に陥り、結局、英語から離れていくことになる。
名刺は1枚、日本語がメインで、英語表記の「おまけ」をつけてみよう。
表面に日英併記でもいいし、表が日本語、裏が英語表記の名刺でもいい。
要するに、1枚の名刺(ビジネスカード)に日本語だけでなく、英語も書かれていることが大事である。
実際、私は、今の職場に配属されて、名刺を渡されたとき、「日本語」しか書かれていない名刺を手渡され、愕然とした。
これでは、英語を使う仕事が来たチャンスを生かせないではないか…と。
そこで、事務所移転を機に、名刺発注の仕事を買って出て、それまでの日本語オンリーだった名刺を、裏面に英語表記につけた日英リバーシブル版に替えてみた。
だから、ビジネス英語への第一歩のたしなみとして「名刺」にこだわってみよう。
2.自分の所属先を英語で
「そんなこといっても自分の部署の英語表記がわからない…」
発注役を買って出たものの、そんな不安が頭がよぎる。
でも、それが大切な「第一歩」である。
自分が所属している部署を英語で言えない人間が、「ビジネス英語」を学習したいというのは本末転倒である。
部署の英語表記がわからないのなら、自分で調べるなり、わかる人に聞くなりして、とりあえず、日本語の名刺を英文翻訳してみよう。
会社が納得しないのなら、自費で名刺を作成してもいい。
けれども会社ロゴの使用とかもあるだろうから、なんとかバイリンガルの名刺発注に死力を尽くしてもらいたい。
理由を尋ねたら、「将来のグローバル化に備えて」でもいい。
また、正直に「英語の勉強がしたくて…」と答えてもいい。
ひょっとしたら、名刺のバイリンガル化を目論むアナタを総務や人事のひとがきちんと見てくれて、英語に関わる仕事に任せてもらえるかもしれない。
チャンスはいつやってくるかわからない。
日本語ではわからない相手や来訪者が来たら、名刺を使うチャンスである。
なかなか英語であいさつするのは難しい。
けれども「バイリンガル名刺」というアイテムがあれば、カタコトでもいいから自己紹介して、名刺を相手に渡す。
当然、連絡先やメールアドレスの情報が書いてあるので、相手にとっても、藁をもすがる思いで、アナタを過日、頼ってくるかもしれないのだ。
そうなればチャンスである。
外国人の顧客から英文メールが私宛に来る…。
これで、勤務時間中でも、堂々と英語を学ぶ時間が捻出できる。
3.まとめ(ビジネス英語の第一歩)
ビジネスの必須アイテム、それは、「名刺」である。
元気な声で、相手の目を見て、しっかりとあいさつ。
そして、あいさつが出来たら、初対面の人には「名刺」を配ろう。
日本人であろうともなかろうとも…。
ビジネス英語への第一歩、それは、日英対訳の「名刺」を持つことからはじまる。
たかが名刺、されど”Business Card”である。