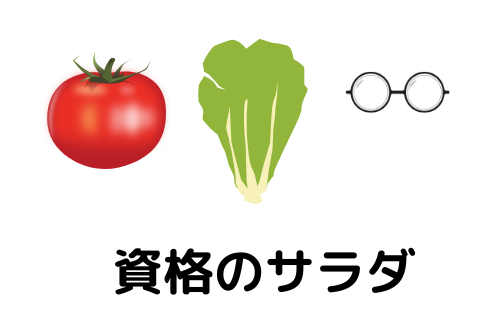時代は変われど、宅建士に求められることは変わらない。
もちろん常に勉強を続けて、変化に対応していかなえればならない。
AIが人間の仕事に取って代わり、リモートワークが進んで対面形式の商談が進み、国際化の進展によって、マーケットが代わりつつある。
そんな中、こうした激しい変化のなか、ますます「宅建士」の役割が重要になってくる。概して、宅建の勉強は、決して無駄にはならないはずである。
1.付加価値の創出
宅建士の資格を持っている人とそうでない人の一番の違いは、その人の「付加価値」である。
宅建士を持つということは、「履歴書」に書ける項目が増えるということにある。
たとえ不動産業界に就職・転職しなくても、採用面接では、人事担当から必ず聞かれることである。
そもそも宅建士の資格自体は、取得者がレアであることが多く、持っているだけで強みになる。
そして、宅建は不動産業界のエキスパートであり、土地・建物の売買や賃貸、民法の知識などは、身に付けていることだけでアドバンテージになり、それを証明する「宅建士資格」は、自分の「売り」になる資格のひとつである。
翻って、なぜ貿易業界に身を置く自分が、業務とまったく関係のない「宅建」の取得をしたのかは、学生時代、民法を専攻したからである。
「ウチのゼミ生ならば、宅建をとりなさい」
そう言っていた恩師の言葉をいつまでも忘れなかったからである。
貿易業界に身を置いても、民法や不動産の知識は、自分の強みを発揮できた。どんな企業でも、不動産の売買や賃貸は不可避な案件であり、そもそも貿易業界は、通関士や貿易実務試験、TOEICといった有資格者がいても、宅建士の資格を持っている人が稀だったため重宝がられた。
そして、何より、自分がアパートを借りたり、マンションを購入したりする際、不動産屋さんを相手に、互角に(自分のペースを死守しつつ)渡り合えたことが、宅建有資格者の何よりの強みになっている。
2.副業時代の不動産知識
昨今のリスキング(学び直し)時代において、資格が注目されている。
宅建士もその資格のひとつ。
ただし、宅建士を取得したとしても、独立や起業は難しいだろう。
不動産業界でもなければ、資格手当もつかないだろう。
けれども、自己啓発が即・自己投資となる昨今において、宅建士を取得するということは、有利に働くことがある。
なにしろ、不動暖の勉強は、金融リテラシーを身に付けることになる。
ただ机上の資格勉強をするだけではもったいない。世の中のつながりといった、大きな視点から試験にチャレンジして欲しい。
たとえば、日経新聞を読む、ということも、宅建士試験の関心を寄せる点で、大きなポイントとなることである。
不動産という血流が、いかに世の中を循環しているか。こればかりは、ただ宅建の過去問題ばかりやっていては、試験のモチベーションが上がらない。経済新聞を読むクセをつけて、世の中の潮流から「不動産」を意識することが大切である。
そして、不動産業界に就職、転職する人はもちろんのこと、それ以外の業界について、宅建試験の動議づけをいかにして維持することができるか。
副業に注目するのも一考かもしれない。
不動産投資、不動産賃貸経営などは、本業で働きながら得ることができる。
お堅い職場(実質的に副業が禁止される)でも、規則によって、不動産賃貸は認められているケースがある。これは、不意に実家を引き継いだり、急な転勤命令によって、自宅を一時的に「賃貸に出す」ことを想定されているものであり、手広くビジネスを展開しなければ、不動産賃貸経営の副収入を得ることができる。
もちろん魑魅魍魎とした不動産ビジネスに打って出ることは、多少の不安があるかもしれない。そんなとき、「宅建の知識」があれば、鬼に金棒である。
今は、不動産賃貸経営の余裕がなくても、将来の「夢」のひとつとして、宅建士の勉強を決意したならば、副収入の夢を描いてもいいのではないだろうか。
3.国際化・AI化と宅建スキル
今後、間違いなく、世の中は、国際化とAI化がますます進展するであろう。
日本の人口は縮小していくので、外国の方々を呼び寄せないと、日本経済は立ち行かなくなる。当然、海外から日本に働きに来る人達は、日本での居住環境が必要となる。
宅建士も国際化の歩調を合わせることが必要となってくる。
何が言いたいかといえば、宅建士を目指すなら、そもそも勉強習慣がある人なのだから、TOEIC(英語)の勉強もしておいた方がいい、ということである。
TOEICも宅建も独学で一定の成果を十分に上がられる資格なので、宅建士を取得を合格したら、即勉強にさよなら、ではなく、TOEIC試験にも触手を伸ばそう。
(目安として、できれば730点以上、最低でも600点以上は欲しいところ)
また、AI時代がくれば、宅建の仕事は、AIに取って代わられるんじゃないか(だから宅建の勉強なんてやってもムダ)という反論があるかもしれない。
宅建士の役割のひとつに「重要事項の説明」がある。
これは、不動産取引において、宅建士が顧客に取引内容を説明することにある。
ここで大切なのは、これはAIよりも、人間的な感情が必要になってくる。
対面にせよ、ウェブ上にせよ、やはりお客さまの「顔色」や「理解度」をうかがいつつ、その人に対しての「カスタマイズ」が必要となってくる。
こうした臨機応変なコミュニケーション能力は、ヒューマンな感情が不可欠であり、これこそが、人間がAIに勝る点である。
ロボットよりも板前さんが作る料理を食べてみたいのが人間なのである。
国際化とAI化が進めば進むほど、より人間的な宅建士が求められるのである。
4.まとめ(これからの宅建士)
リスキングが叫ばれる一方、社会人の平均勉強時間は6分といわれる。
勉強する人とそうでない人の二極化が進んでいるように思われる。
宅建士は勉強しなければなれない。
さりとて、弁護士のような取り立てて難関な資格というわけではない。
勉強習慣さえ確立していれば、独学でも十分可能な資格である。
宅建士試験に合格した暁には、「自分の付加価値がつく」「副業の夢が広がる」「国際化やAI化に淘汰されない」という自信が沸いてくる。
ぜひとも宅建士の勉強を決意した人は、合格までやり遂げることを期待したい。